日々の読書から、おすすめを紹介します。今日は、
『静かな退職という働き方』
2025年03月初版
1.著者
海老原嗣生
サッチモ代表社員
雇用ジャーナリスト
2.どんな期待を持って読んだか
静かな退職の解説をしたPivot動画をきっかけに、
これからの労働を考えるきっかけを得られると思いました。
なお、「静かな退職」という言葉について、
読む前は、「働かないおじさん」イメージを想像していましたが、
そうではありません。
20代、30代をイメージしましょう。
もっとポジティブなイメージです。
3.構成
第1章 日本にはなぜ「忙しい毎日」が蔓延るのか
第2章 欧米では「静かな退職」こそ標準という現実
第3章 「忙しい毎日」が拡大再生産される仕組み
第4章 「忙しい毎日」を崩した伏兵
第5章 「静かな退職」を全うするための仕事術
第3章 「忙しい毎日」が拡大再生産される仕組み
第4章 「忙しい毎日」を崩した伏兵
第5章 「静かな退職」を全うするための仕事術
第6章 「静かな退職」の生活設計
第7章 「静かな退職」で企業経営は格段に進歩する
第8章 政策からも「忙しい毎日」を抜き取る
4.全体的な所感
日本の労働環境を、欧米と比較することで、
日本の「働く」が世界で例外的であることを
知ることができます。
日本の人口増加×高度経済成長の時代では、
良かった人事制度が、
人口減少×低成長の時代にそぐわないことを
理解することができます。
日本の働くの長期予測であり、
私も同じような未来を期待しています。
著者としては、
最後の出版を想定していますが、
きっと次作を書いてくれるでしょうし、
心からの期待をしたいと思います。
5.個別の印象的な内容
P52より、
ドイツの場合、職業資格数は400ほどあり、
学歴も~そこそこ融通が利きはします。
対してフランスは、職業資格数が8000もあり、
学業代替プログラムもないため、横にも縦にも転職が大変なのです。
P188より、
生産性アップには、分母となる労働時間を減らすのが一番効果的なのに、
未だに分子の「成果」を増やす方に目を向けてしまうのです。
P190より、
欧州型の賃上げシステム(企業横断型の労働組合が職種別に賃金を決める)
だと、企業は賃上げを甘んじて受け入れられるのです。
「ライバル他社も一律賃上げならば、安心して価格転嫁ができる」
からなのです。
ちなみに、日本は企業別に賃金が決められています。
6.おすすめなのか
特におすすめしたいのは、
2つのペルソナです。
①
特に企業の人事におすすめしたいです。
報酬制度の設計段階で、本書の時代認識ができれば、
年功制度を根底から修正することができるようになり、
適切な人事戦略を立てることができると思います。
大企業のキャリアパスは、
マネジャーラインとプロフェッショナルラインの
2本とする会社が多くなってきています。
プロフェッショナルラインについて、
仕事の難易度が上がり、給与も上がる人もいれば、
仕事の難易度が変わらず、給与もあがらない人も
いていいという制度を作ることが大事だと思います。
②
女性の子育て世代の総合職におすすめしたいです。
彼女たちは、そう思っていなくとも、
「静かな退職という働き方」をしている人は多いと思います。
天職ではなくても子供を育てるために、
仕事に熱中するわけでもなく、組織と共に歩んでいく人たちは、
飲み会はおろか、残業もなかなかできません。
しかし、それでいいんだと私は思っています。
それが、これからの日本には必要なのだと思っています。
子育て世代の男性に次を自問させることで、
生産性の悪さを自覚することができるからです。
・このサービス残業は本当に意味があるのだろうか?
・なぜこの根性論みたいな仕事をやっているのだろうか?
・毎年の惰性でやっている仕事、やる意味あったっけ?
という悲しい現実を直視させるからです。
ありがとうございました。
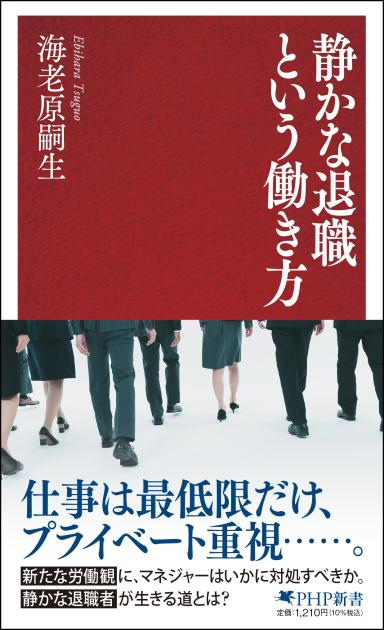
0 件のコメント:
コメントを投稿